
Interview #
12
2025
年
9
月
田中聡
Satoshi TANAKA
ディオントーキョー
代表取締役
―田中さんの長いサーチ活動が終わり、ついにディオントーキョーを承継し晴れて経営者として参画することになります。中小企業に外様社長として入る難しさは大きいと思います。就任直後、最も気を遣った点は何でしたか?
(田中)巻島さんをはじめ、いろんな人から「やわやわと入れ」「焦らんでええ」と助言されました。だから最初からガツガツと自分を出すことはせず、まず「従業員の皆さんを知る」ことに徹しました。結局すべては人。どんな人がどんな思いで働いているのかを理解するところから始めました。幸い、前オーナーが半年間残ってくださったのも大きかったです。私は端の席に座り、メインの座席は前オーナーに座り続けてもらいました。資金管理や労務などのバックオフィス業務は私が担当しつつ、金回りだけは必ず押さえる。最初の半年間は、現状把握を丁寧に行い、商流や金繰り、オペレーションルーティンを把握することに専念しました。
―半年後、前オーナーが勇退されたあと、リーダーシップはどのように移行していったのでしょうか?
(田中)ちょうどオフィスの移転があり、座席配置を変えたとき、自然に変わっていきました。ただそれでも、自分が真ん中に座ることはせず、マネージャー陣をメインに座る形にしました。社長が「主役」であるような見せ方はやめるようにしました。私はマネージャー陣と密にやり取りをし、他の社員とのコミュニケーションは、マネージャー陣から行ってもらう様な体制を取りました。その中でも、自身の経験が生かせる領域である営業部門に対してはたくさんのコミュニケーションを取るようになりました。
-具体的にはどのようなコミュニケーションを行ったのでしょうか
(田中)営業は会社の数字を背負う部門です。営業部のマネージャーには価値観の軸として大きく2つ。①必要以上に「品質がいい」と誇張するな、②「いい顔値引き」はするな。ということを伝えました。虚偽や安売りでは長続きしない。良いものを売ってるんだから、堂々と物を売ろう、ということを伝え続けました。

-なるほど、田中さんが営業で酸いも甘いも経験したからこそ伝えられることですね。その他に手掛けたことについて教えてください
(田中)細かくは色々とあります。例えば、アフターフォロー体制の強化です。よくある中小企業では、トラブルが起きたらその場で火を消す「ボヤ消し」に終始します。でもそれでは何度も同じ火事が起こる。私は常に「なぜボヤが起こり、どうすれば再発を防げるのか」「ボヤが起きたときに場当たり的ではなく、安定して対応できる体制をきちんと作ろう」と問い続け、少しずつ形になってきています。
また、取引先との支払い条件も変えました。お客様にご納得いただき一部を機器の設置前に代金を頂くことにしました。資金繰りが安定しないと経営は続けられませんから。
-本当に小さなことの積み重ねですね
(田中)結局は“1を2に、2を2.5に積み上げる”地道なノウハウの蓄積です。派手さはありませんが、これができるかどうかで企業の未来は決まります。経営はきらびやかな戦略立案よりも、日々の入出金と組織マネジメントで全てが決まると思っています。火を消し続けるだけでなく、火が起こらない仕組みを作ること。営業は虚偽や値引きに逃げずに売ること。華やかではありませんが、そのノウハウの蓄積こそが中小企業経営の核心だと思っています。
―今後の経営方針についても教えてください
(田中)収益を安定化させることを第一に考えています。企業体力に見合わない無理な成長を追い求めるのではなく、品質を高め、安定的にキャッシュフローを生み出す会社であることが大切だと思っています。
大事なのは「良いものを売る」という姿勢。それは商材だけでなく、フォロー品質も含みます。設置店に喜んでもらえるイベントや、販売後のアフターフォロー体制を整え、結果として、「この会社に頼めば売った後も安心だ」と思っていただけるようになれば、機器を導入していない店舗からも相談をもらえるようになる。そういった業界内でのポジションを確立することを目指しています。営業の強みは「丁寧さ」です。お客様と誠実に向き合う。だから設置後にトラブルがあっても「この会社は最後まで対応してくれる」と信じてもらえる。良いものを売っているわけですからこれを徹底していれば、自然と数字はついてきています。
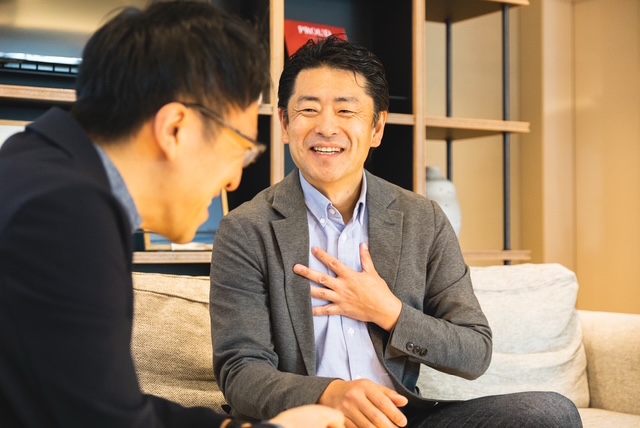
―ありがとうございます。田中さんはこれまでも多くの企業で経営者として活躍してきました。経営スタイルは以前の経験とどう変わりましたか?
(田中)一番の違いは「主役じゃなくなった」ことです。若い頃は自分が前に出てイズムを注ぎ込むタイプでした。でも今はそうせず、マネージャー陣が活躍できるフィールドを自分が整えることに専念しています。「自分が社長だったらどう思う?」と問いかけ続けています。単なる部門担当ではなく、経営者視点で判断できる人材に育ってほしいからです。彼らが経営者としての見方を持ってくれるからこそ、この会社はもっともっと強い会社になっていくと思います。これは今の年齢だからこそできるスタイルかもしれません。
―経営者としての孤独についてはどう感じていますか?
(田中)経営者は孤独です。これは仕方がない。補ってくれるのは仕事外の活動です。私の場合は役者活動ですね。舞台に立ち、全く違う世界で体を使うことでリフレッシュしています。経営と舞台稽古と、体力的にもキツイ部分もあるのは事実ですが、役者としての挑戦が良い意味で経営にも跳ね返ってきている気がします。
―最後にお伺いしたいのは、経営者としての覚悟についてです。田中さんご自身、これまでも厳しい局面をたくさん経験されていますが、今後サーチファンドに挑戦する人たちに向けて、「どういう人が乗り切れるのか」「どんなマインドが必要なのか」、そのあたりをどう考えていらっしゃいますか
(田中)正直、経営なんて運の連続もあると思います。今こうやって経営者として立って話していますけど、状況によっては違う結果になっていたかもしれない。明日はどうなっているか分からない。だから一概に「こうすれば成功する」というものはないと思います。
ただ、ひとつ大事なのは「自分との折り合い方」だと思うんです。自分とどう折り合いつけるか。例えば、資金繰りが苦しくなって役員報酬をゼロにする状況が来たとします。そのときに「自分の貯金が尽きるまでやりきって、それでもダメなら仕方ない」と腹をくくれるか。私はそういう覚悟を持って取り組むことが重要だと思います。
もちろん、経営者がそこまで自分を追い込むべきかどうかは別の問題です。心身や家庭を壊してまでやることではない。ただ、自分がゼロ報酬で半年耐えるくらいでは死なないし、それくらいの覚悟でやりきった上で「無理でした」と言えば、周囲も納得すると思うんです。投資家も「そこまでやったなら仕方ない」と割り切れる。そういう生き様としての帰結まで見据えたうえで挑戦できるかどうかはかなり重要だと思います。
―それは、経営者としての「リスクを取る姿勢」を問うているということですね
(田中)そうです。リターンだけ欲しい、自由だけ欲しい、経験だけ積んで次のキャリアのジャンプ台にしたい――そんなマインドでは難しいと思います。投資家からリターンを受け取る権利だけ主張して、リスクは一切負いたくない。そんな「雇われ」的なスタンスで経営に臨むと、結局うまくいかないと思います。
だから、個人保証を入れるとか借金を背負うとか、そういう極端な話ではなくて、「自分自身もリスクを分かち合う」という感覚を持てるかどうか。そこに本気度が表れると思います。
そのうえで企業が成長し、お客さんにも喜んでもらい、従業員とも喜びを分かち合える瞬間、それは経営者でないとみることができない景色です。自分の生き様として挑める人にこそふさわしい挑戦だと思います。自分の覚悟を試したい人にとって、サーチファンドは最高の挑戦になるはずです。

--
▼田中聡氏(ディオントーキョー代表取締役)連載インタビュー
vol.1 | 挫折と挑戦、その先に ―プロ経営者が選んだサーチファンド
#
13
#
12
#
11
#
10
#
9
#
8
#
7
#
6
#
5
#
4
#
3
#
2
#
1